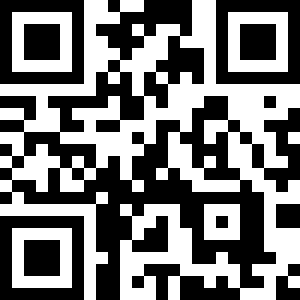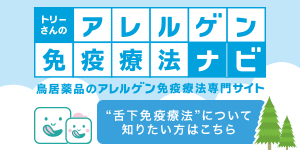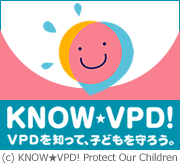活動
研究会での講演
- 第1回 学習会の運営に関して
2005年2月 - 第2回 地域支援に必要なこと
2005年3月 - 第3回 AD/HDの理解と対応
2005年4月 - 第5回 特別支援教育について
2005年6月 - 第6回 広汎性発達障害Part1(診断)
2005年7月 - 第7回 広汎性発達障害Part2(治療)
2005年8月 - 第8回 発達障害の告知の問題
2005年9月 - 第9回 学習障害Part1(学習障害について)
2005年10月 - 第10回 学習障害Part2(軽度発達障害児の診断と評価)
2005年11月 - 第11回 就学前の子ども支援について
2006年1月 - 第13回 反応性愛着障害についてPart1
2006年3月 - 第14回 反応性愛着障害についてPart2
2006年4月 - 第15回 反応性愛着障害についてPart3(ペアレントトレーニングについて)
2006年5月 - 第16回 ペアレントトレーニングについてPart1(実践編)
2006年6月 - 第17回 ペアレントトレーニングについてPart2(トークン表について)
2006年7月 - 第20回 フィンランドに学ぶ
2006年10月 - 第21回 「いじめ」について考えるPart1
2006年11月 - 第22回 「いじめ」について考えるPart2
2006年12月 - 第23回 子どもの発達といじめについて
2007年1月 - 第24回 心身症について「睡眠について」
2007年2月 - 第25回 心身症について「痛みのメカニズム 腹痛 過敏性腸症候群など」
2007年3月 - 第26回 心身症について「起立性調節障害について」
2007年4月 - 第27回 心身症について「夜尿症・遺尿・遺糞・心因性頻尿について」
2007年5月 - 第28回 心身症について「アトピー性皮膚炎」
2007年6月 - 第29回 軽度発達障害の子ども達(総論と事例)
2007年7月 - 第30回 軽度発達障害の子ども達(各論と事例)
2007年8月 - 第33回 心身症について「チックについて」
2007年11月 - 第34回 ラプシー研究会への提言
2007年12月 - 第36回 不登校の事例について(軸診断 Part1)
2008年2月 - 第37回 不登校の事例について(軸診断 Part2)
2008年3月 - 第41回 子どもの発達と行動の理解(Part1)
2008年7月 - 第42回 子どもの発達と行動の理解(Part2 行動療法の活用について)
2008年8月 - 第43回 子どもの発達と行動の理解(Part3 行動療法の活用について)
2008年10月 - 第48回 平成21年度の研究目標と日程について
2009年3月 - 第49回 困っている子どもたちへの対応(多次元評価と具体的対応について)睡眠について(睡眠と薬物について)
2009年4月 - 第50回 事例検討を通じて多次元評価の検討
2009年5月 - 第52回 多次元評価による検討(事例の分析)
2009年7月 - 第53回 多次元評価による検討(無関心を適応に向けるための方略)
2009年9月 - 第54回 多次元評価による検討(過剰反応を適応に向けるための方略)
2009年9月 - 第59回 多次元評価による検討(子ども-学校-家庭との連携 事例検討)
2010年2月 - 第60回 ラプシー研究会の今後の展望2010(チャートを利用した事例検討)
2010年3月 - 第61回 愛着形成と子どもの発達
2010.4.24 - 第64回 次元診断とチャートの検討
2010.7.10 - 愛着を究めるための実践
2011.2.26 - (1)災害時のメンタルヘルス・教職員と保護者がしっておきたい災害を体験した子どもたちの心のケア
(2)アメリカ視察報告・愛着を究めるII
2011.5.21 - 愛着障害について―ACTトレーニング―
2011.9.10 - 愛着を究める―事例編―
2011.10.15 - 第83回 「修復的愛着療法ワークショップ」事前講習会
2012.4 - 第84回 第3回修復的愛着療法ワークショップ ―絆の修復に向けて―
テリー・Mーリビィー心理学博士
マイケル・オーランズ臨床心理士
ヘネシー 澄子先生
2012.5.4~6 - 第86回 事前検討会を通じて地域連携を考える
2012.7.7 - 第87回 「心にふれあう子どもたち」―ACTトレーニング―
2012.8.4 - 第90回 「子どもとかかわる・チャートの活用」
2012.11.17 - 第92回 「コーディネート力を高めるために」
2013.1.12 - 第94回 「子どもの成長のメカニズム」
2013.3.9 - 第95回 「発達障害について」行動療法の理解 パート1
2013.4.13 - 第96回 「発達障害について」行動療法の理解 パート2
2013.5.18 - 第97回 「身体疾患と行動について」
2013.6.15 - 第98回 「身体疾患と行動について」超立体性調節障害について
2013.7.6 - 第99回 「身体疾患と行動について」不定愁訴について
2013.8.3 - 第100回 「ACTトレーニングについて」
2013.9.7 - 第104回 「問題を抱える子ども達の親とともに歩む」
2014.1.18 - 第107回 ACT 子供の会話について
2014.4.19 - 第108回 次元診断 2014PART1
2014.5.17 - 第109回 次元診断 2014PART2
2014.6.28 - 第110回 基礎からのACT PART1
2014.7.12 - 第111回 基礎からのACT PART2
2014.8.23 - 第112回 新次元診断
2014.9.6 - 第116回 連携の実際について<子どもの心に触れる>
2015.1.17 - 第117回 ASD児のコミュニケーションの発達
2015.2.8 - 第118回 最近の愛着障害の理解
2015.3.7 - 第119回 神経発達障害の理解について
2015.4.25 - 第120回 新しいADHDの理解について
2015.5.16 - 第122回 新しいASDの捉え方について Part1
2015.7.25 - 第123回 新しいASDの捉え方について Part2
2015.8.29 - 第127回 ACTトレーニング
2015.12.26 - 第128回 子どもの遊びや脳の発達について
2016.1.28 - 第129回 教育現場のつながりを求めて
2016.2.13 - 第131回 次元診断を通じて事例検討を考える
2016.4.23 - 第140回 子どもの成長
2017.1.21 - 第147回 脳を育てる<自己評価を高めるために大切なこと>
2017.8.12 - 第152回 脳を育てる<生活面からのアプローチ>
2018.1.13 - 第153回 脳を育てる<運動や学習面からのアプローチ>
2018.2.17 - 第155回 コントロールされて生きる
2018.4.14 - 第159回 自己の気づきとモーターコントロール
2018.8.4 - 第164回 「脳の発達に基づいて子ども達一人ひとりが持っている視点を育む方法」0章 ガイドライン
2019.1.26 - 第165回 「脳の発達に基づいて子ども達一人ひとりが持っている視点を育む方法」
1章 脳の発達のメカニズムについての総論 Part1
2019.2.23 - 第167回 「脳の発達に基づいて子ども達一人ひとりが持っている視点を育む方法」
1章 脳の発達のメカニズムについての総論 Part2
2019.4.13 - 第168回 「脳の発達に基づいて子ども達一人ひとりが持っている視点を育む方法」
2章 発達行動療法 総論
2019.5.25 - 第169回 「脳の発達に基づいて子ども達一人ひとりが持っている視点を育む方法」
2章 発達行動療法 各論
2019.6.8 - 第170回 「脳の発達に基づいて子ども達一人ひとりが持っている視点を育む方法」
2章 発達行動療法 各論 Part2
2019.7.6 - 第171回 「脳の発達に基づいて子ども達一人ひとりが持っている視点を育む方法」
4章 コミュニケーションの総論
2019.8.24 - 第172回 「脳の発達に基づいて子ども達一人ひとりが持っている視点を育む方法」
4章 コミュニケーションの総論 Part2
2019.9.28 - 第173回 「ACTトレーニング」
4章 コミュニケーションの各論 Part1
2019.10.26 - 第176回 令和2年1月25日(土)14:00~17:00
久喜市清久コミュニティセンター 西公民館 研修室1 参加者15名
「第3章 遊びのプログラム 総論」
自己コントロールを楽しもう<運動·遊び編> - 第177回 令和2年2月22日(土)16:00~18:00
奥山こどもクリニック トレーニングルーム 参加者11名
「第3章 遊びのプログラム 各論」
自己コントロール力を高める -体編ー
※世界的なコロナの流行により、対面による活動を休止していました。 - 第178回 令和3年9月18日(土)15:00~17:00
ズームによる交流会 参加者6名
小児科医が教える子どもの脳の成長段階で「そのとき、いちばん大切なこと」 - 第182回 令和5年2月18日(土)15:00~17:00
新しい次元診断 Part1
<困り感のある子どものとらえ方> - 第183回 令和5年3月11日(土)15:00~17:00
新しい次元診断 Part2
<困り感のある子どものとらえ方>
-子どもたちの不安のメカニズムを解くー - 第184回 令和5年6月17日(土)15:00~17:00
今後のラプシーの活動について
<まずは現状の事例検討会から始める> - 第185回 令和5年7月29日(土)15:00~17:00
「事例検討会」
-あるADHDの子どものケースを通じてー - 第187回 令和5年8月26日(土)15:00~17:00
「事例検討会」
-あるASDの子どものケースを通じてー - 第188回 令和5年12月23日(土曜日)15:00~17:00
発達行動療法を学ぼう